年末に第九を聴く習慣は特にないのだけれど、2022年の12月31日はちょっと聴いてみた。
第九の4楽章ではシラーがフランス革命の直前に書いた詩の一部が抜粋されている。神に対し最大級の賛辞を述べながらも、この作品の主人公は地上に生きる人間であるという点が特徴だ。神やイエスキリストの御業を歌い上げる他の多くの宗教曲と一線を画しており、キリスト教を念頭に置きながらもより多く人間賛歌であるという特徴を持っている。
聴いたのはフリッチャイとベルリンフィルで、1958年の録音。名盤の誉れ高く、フリッチャイの精緻でピュアな音楽づくり、ベートーヴェンへの尊敬にあふれており、そしてフルトヴェングラーが死去してからさほど時が経過していないベルリンフィルの硬質かつ峻厳で緊張感の高いサウンドに感銘を受けた。

卓越した音楽センスとたぐいまれな統率力でベルリンフィルを天空まで舞い上がらせていくフリッチャイの棒さばきにわたしが余計な付言を加える必要もない。でもちょっと言いたくなったので書こう。この演奏は神に愛されている。ベートーヴェン音楽の真髄に迫ることのできる音楽家は数少ないが、フリッチャイはそれにたやすく手を触れることのできる一人だ。交響楽に内在する核心に彼は苦もなくアクセスし、その本質をオーケストラを媒介とした美しい音で再現して見せる。
神はディテイルに宿る、とよく言われる。ではフリッチャイは細部を磨き上げることに技術的な腐心をしているのかどうか。聴くかぎりそうは感じられなかった。思うに彼が産み出す音楽そのものが美であるがゆえ、ディテイルを磨く必要がなかったのだろう。
神に愛された作品であれば、作り手が手間をかけずとも(リハーサルをサボっているという意味ではもちろんない)、その細部に神はごく自然に宿っている。そう思わせる演奏だった。
仕事がらみの長い間引きずっていた人間関係の古傷が昨日から再発していた。すでに解消された問題の心的な後遺症のようなもので、もう傷自体は痛まないものの、嫌な記憶を反芻する癖で、我執が自分の意思を妨害しようと蠢動しているのだった。
聴いている最中もそれが意識の上層に上がってきて感興を邪魔する。取り去りたいのだけど外れてくれなくて、聴きながら困っていた。
というわけでフリッチャイのだけでは聴き足りなくて「もういっちょ聴いとくか」となり、今度はフルトヴェングラーの「ルツェルンの第九」を、奥に閉まってあったのを引っ張り出してCDプレイヤーに載せた。
フルトヴェングラーは長くベルリンフィルを率いてきた。後を継いで首席指揮者になる候補の一人に、フリッチャイも上がっていた。他にチェリビダッケやカラヤンといった名が出ており、最終的にカラヤンがその座についたが、フリッチャイの指揮スタイルはフルトヴェングラーのやり方に近しいものがあったという話を、どこかで読んだことがある。
ルツェルンの第九も聴いていてよかった。久しぶりに聴いた。
というよりも第九自体、かなり久しぶりに聴いた。わたしは1~3楽章は好きなのだけど、4楽章はもうほぼお付き合いで聴いているような感じで、人類愛を高らかに歌い上げる的なムードにどこか違和感があり、シラーの詩も取って着けたような美辞麗句の集合体のようで、ヘタな演奏に合うと大衆迎合的な雰囲気がテキメンにあらわれてしまい、気高さが大幅ダウンしてしまうというのがわたしの4楽章の感想だ。曲の主旨から少し音楽性の敷居を下げた感じが4楽章には漂っている、と思っていて、ベートーヴェンがそれを知ったら怒り心頭だろうけれど、第九を聴くときは、彼ももう成仏してるんだろうからそこまで怒ったりはしないかな、とか思いながら聴くのだった。
4楽章の最も壮大な場面は10分過ぎぐらいで合唱が「vor Gott」を高らかに歌うところで、とりわけフルトヴェングラーはここを最大の山場にしているように思う。霊的な高揚が最高潮に達する場面だ。
Und der Cherub steht vor Gott !
そして神の御前には智の天使ケルビムが立ち給う!
(アルバムのライナーノートより。渡辺護訳)
ベートーヴェンもシラーもヨーロッパの人だからキリスト教なのだが、ギリシャ神話の楽園エリュシオンの語にあたる「Elysium」があったり、「美しき神々の閃光よ」といった詩句もあったり、上で引用したように神を指す詩句に Gott という語彙を当てていることから、あえてキリスト教的唯一神・救世主に限定することなく、他の宗教に見られる超越的な統率者、全知者、覚知者的な概念をそこに当てるのも後世のわたしたちの自由だろう。地域的で血縁的な狭い領域にとどまらずに世界化していったヨーロッパの文明文化の特質がそうさせるという面もある。
じっさい、合唱が「vor Gott」と大斉唱する時の“神”のイメージは聴いていてたいへん抽象化されたものを感じる。高揚し絶頂に達した旋律が放つ波動はどの宗教の神でもなく、そうであるがゆえにどの宗教の神でもあるというニュートラルな次元へと跳躍している。いわばここは最高次元へアセンションしていく魂のありさまを音楽的に具現化した瞬間だと思われる。
だからこの強烈なクレッシェンドが終止した後にひろがる巨大な静寂は、ある意味第九の最大の聴きどころなのかもしれない。
この部分はフリッチャイの場合、最高位の音楽的陶酔の中で、軽やかな天使の羽根のように音全体がクレッシェンドしていく。何の重さもなく、きわめて軽い次元上昇。スッと浮き上がるような感じだ。たいへん心地よい。
そしてフルトヴェングラーの「ルツェルンの第九」では、これは「バイロイト」もそうだけど、圧倒的で強大な推進力で地上からリフトアップしていく感じで、強靭な遺志と崇高な精神が存在界のすべてを鳴動させながら飛翔していくかのようなダイナミックでパワフルな斉唱となっている。
両者はまったく違う印象。
フルトヴェングラーの第九ライブ録音でわたしが持っている最晩年時にウィーンフィルと共演したものを先ほど聴いてみたが、このパートの高揚感はルツェルンやバイロイトと同じ質のものだった。
しかし1942年3月のライブ録音、有名な「総統の第九」よりもちょっと前に行われたコンサートということになるが、この演奏でのクレッシェンドは、神への希求の手が伸ばされていくような、一筋の光をつかもうとするかのような、強い切迫感、ひっ迫した感じ、切ない感じに似たなにか、になっている。聴き直してみて非常に驚いた。おそらくは第二次大戦中の演奏という要因がかなり作用しているだろう。異常なまでの緊張感だ。(戦時中のフルトヴェングラーの録音は、第九に限らず他の曲でも、戦乱の影響を強烈に受けたと思われるものが多く残っている)
この大斉唱が終止した後にテノール独唱が始まる。超越者が世界の向こう側にリープしていく瞬間を垣間見た人類が、いまある足元の苦悩から再び希望をもって、この世界を一歩一歩踏みしめながら歩み出す姿が感じられる。曲はあの場面でいったん終わって、テノール独唱からまた人類の新たな物語が再スタートを切る、といった感じだろうか。
ケルビム。旧約聖書創世記で神は「善悪の知識の木」の実を食べたアダムとエバをエデンから追い出した後に
命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムと、きらめく剣の炎を置かれた。
(創世記3:24)
と、ここでケルビムが登場している。
他に、出エジプト記にもケルビムの姿をした装飾品が出てくる。インディ・ジョーンズの映画に出てくる聖櫃の飾りつけだ。また、エゼキエル書に描かれるケルビムは異形の怪物さながらで、これらを概観すると、神の前にあらわれるケルビムとは、神の威厳を示し、同時に人間を見張り、人間が近づけないようにする威嚇のような機能を備えている天使のようだ。
神の前にケルビムが立つ……造物主が住む至高の聖域に被造物たる人間は踏み入らせないとでもいうのか。
vor Gott ! の壮大なクレッシェンドは人間が本来描きえない聖別された超越的な領域を音楽によって具現化してみせた稀有な瞬間でもある。燦然たる神の領域を垣間見たのち、自分の足元にひろがる惨めな地面に人類は落胆する。ここから再スタートだ。人間界の3次元的な格闘戦を音楽は描く。
人類は前進し、つまずき、苦しみ、また喜び、さらに歩を進め、傷ついて、悲しんで、そしてまた希望に満ちて、また前進していく。その様子が描かれたのち、作品は終わりに近づき、終結部のきわめて人間的な歓喜と祝祭的な音響世界があらわれる。
ベートーヴェンはコーダのテンポ設定にプレストを指定しているが、フルトヴェングラーのここの解釈はわたしが聴いたことのあるどの録音もいわゆる「オケが壊れてる」状態になるほどの疾走感で駆け抜けるというものだ。
フ氏は「ここでオーケストラは壊れなければならない」という固い信念を持っているかのようだ。晩年のフルトヴェングラーの演奏はどの録音もかなりおっとりしたテンポ設定だが、第九のコーダに関しては一貫してオーケストラが機能しないほどの速度でいっさんに飛ばしていくスタイルを堅持している。あと少しでもはや音楽ではなくなってしまうまでフルトヴェングラーはアクセルを踏み込むのだ。
演奏そのものを台無しにしかねないほどの高速テンポで、フルトヴェングラーはわたしたちを“音楽の向こう側”まで連れて行ってくれる。
もしかしたらベートーヴェンも、自分が構築した巨大な音楽的大系、いや人類が築いてきた文明の大系そのものが崩壊しなければ、人類が経験し得る最高次元での歓喜には到達できないと感じて、ここにプレストを指定したのかもしれない。音楽を音楽そのものによって破壊しない限り、歓喜はただ単に人間どもの乱痴気騒ぎに終わるだけで、「vor Gott !」の至高の領域に到達することができないのだと。
みずからが構築した大系をみずからの手で破壊しなければ、そこにはたどり着けないのだと。
大天使ケルビムとは智天使。此岸と彼岸を分けるものはなにか?それは、みずからを破壊し、否定する智慧なのか?
すべてを取り去り、ゼロポイントに立ち戻ったところからこそ「vor Gott」の至上の喜びに到達できるのだとしたら?
破壊と消滅、そして新たな誕生の果てしないプロセスがわたしたちの生命を働かせているのだとしたら?
第九の第4楽章は破壊と再生を描いている、というのが2023年年初のわたしの当面の結論だ。

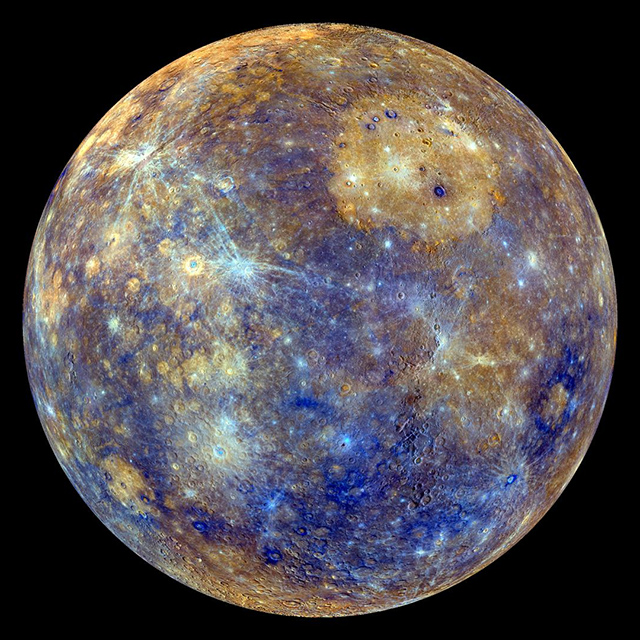

コメント